皆さんこんにちは。
今世間では生成AIが話題になっていますね。
テキストを生成するAI「ChatGPT」や画像生成AI「DALL·E」
特に私たち映像業界の人間を驚かせたのが、動画生成AI「Sora」の登場でした。
動画生成AI「Sora」とは
生成AIのOpenAIが開発した動画生成AI。プロンプトを書くだけでその指示に従ってAIが動画を作り出すことが出来る。
あの映像を観た人の中には映像業界がAIに取って代わられると思った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし結論から言うと、取って代わるという事は今の現状で私は無いと考えています。
ではなぜそう言えるのか?
その理由をAIの現在地を見ながらお話ししていきたいと思います。
- AIの現在地
- AIの苦手分野と得意分野
- 映像業界におけるAIの役割分担
- AI登場による懸念点
動画生成AI「Sora」登場で業界騒然⁉ AIは映像業界を滅ぼすのか?
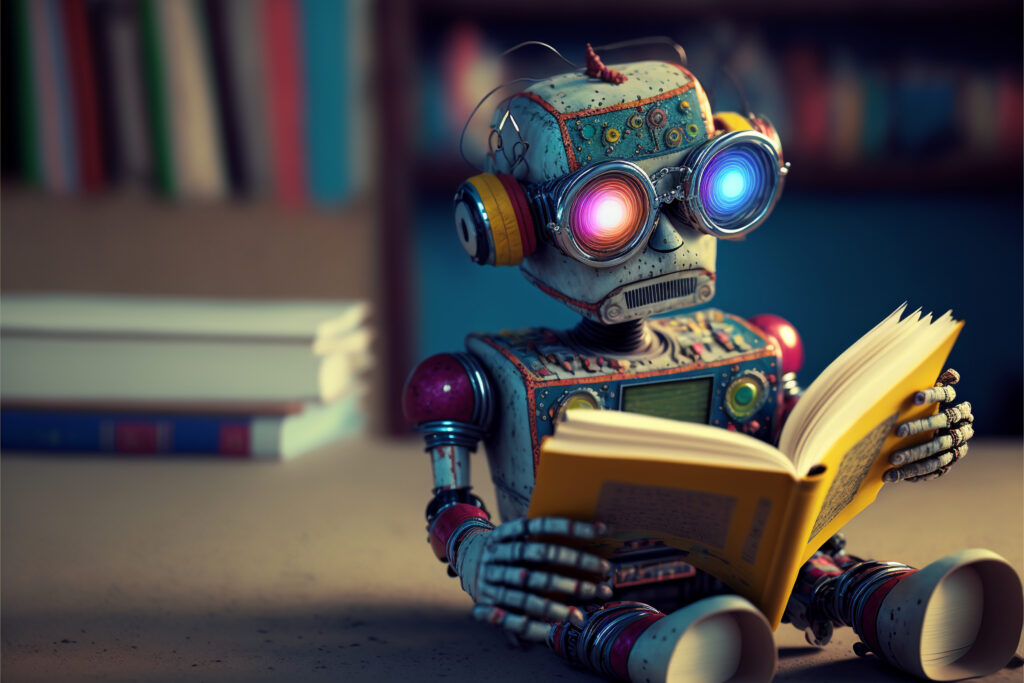
AIの現在地
生成AIのニュースなどを見ているとAIで何でも出来てしまうんじゃないかと錯覚してしまいそうになりますが、現状そこまで万能とは言えません。
生成AIの原理として大規模なデータを収集し学習する事で、その学習したデータを元に言語や映像を生成する仕組みになっています。
たまに未学習なものでAIの中にデータが少ない場合がありますが、その時のAIの回答はかなり曖昧で、それらしいもので済まそうとします。
この人間の持っている「ひらめき」や「創造性」を必要とするゼロから創作する事が、AIにとって現時点では苦手分野とされています。
また、この学習においても著作権や肖像権の観点から規制する動きも強まってます。
特にデジタルデータの作品などAIに学習させないようにブロックするようなアプリも開発されています。(2024.6月現在)
つまり「膨大な過去のデータから構成された新しい物」を作るのは得意ですが、過去との流れを汲んでいる創作物であり、ゼロイチで何かを作り出す事は現状出来ないという事なのです。
なので、とても緻密で本物と見まがう映像を作り出せたとしても「どこかで見たことある」ものや「想像の範囲内」のものでしか無いのです。
そういう意味でゼロイチの創造性をもつ人に歩があるのです。
では生成AIは映像では全く使えないのでしょうか?
そんなことはありません、AIの得意分野を生かすことで映像業界も大きく変化すると思います。
特にAIの得意分野は「データ収集」「管理」「生成・要約」「模倣」です。
この得意分野をAIに役割分担する事で今後映像業界もかなり働き方が変わってくると思われます。
では今後起こり得る映像業界での生成AIの役割を考察してみたいと思います。
映像業界でのAIの役割分担

生成AIの得意な事として「データ収集」「管理」「生成・要約」「模倣」です。Microsoftの生成AIがCOPILOT(副操縦士)と名付けられているように人間の補佐、作業効率を効率化することに特化していくと考えられます。
下記に映像業界でAIが得意そうな作業を並べてみました。
※注)あくまでも想像上の一例です。
【データ収集・管理】
・脚本の時代考証や設定の監修、文章校正
・オーディションの収集、選定、管理
・撮影スケジュールの構成、管理
・ロケ場所の収集、管理
【生成・要約】
・アイデアの大量作成
・企画書の作成
・設定書の作成
・宣伝、物販物の作成
・字幕翻訳
【模倣】
・美術小道具の原稿作成
・劇中小道具の作成
・合成の処理の効率化(トラッキング・マスク等)
・合成下画の生成
このようにAIにおいてゼロイチの創造性を求めるのではなく「作業の効率化」「コスト削減」による「完成度の向上(生産性の向上)」を目指す事が最も良い使い方でないでしょうか。
これにより、人はよりゼロイチの創造性に集中することが出来ます。
それにこれは個人としてもかなりの強みになります。
いままで、組織的に動かす事で可能だった仕事が個人でも可能になるという未来です。
一人で映画スタッフ何人分の能力が手に入るようなものなので、個人クリエイターとしてはかなりの武器を手にすることが出来るかも知れません。
しかし、一方で懸念点もあります。
AIの浸透による懸念点
それは恒常的に日本の映像業界の悪い習慣である「経費削減による作品の低予算化」です。
これは以前「民生機のビデオカメラ」が登場した時も起こりました。
安価で簡単に撮影できる機材が登場したことで一斉に映像制作会社が自社のカメラを持ち、低予算で作品を作り始めたのです。
確かに作品数は爆発的に増えましたが、その分一作品のクオリティが下がり、スタッフのギャランティも減っていきました。
またコストのかかるプロのスタッフはセミプロのような経験の浅いスタッフに置き換わっていきました。
これに似た様な事はAI時代においてもやはり、起きてくることでしょう。
それは「完成度の向上」とは真逆の「作品の質の低下」につながります。
AIであっても使い方や、使う側のモラルにより作品の良しあしは左右されるという事ですね。
AIの登場により格段にコストパフォーマンスは向上するでしょう。
しかしそれが現場環境の改善、生産性の向上をもたらすのか、コスト削減で現場環境を悪化させ、作品の質を低下させるかは結局のところ人間次第なのかもしれません。
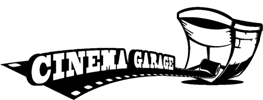
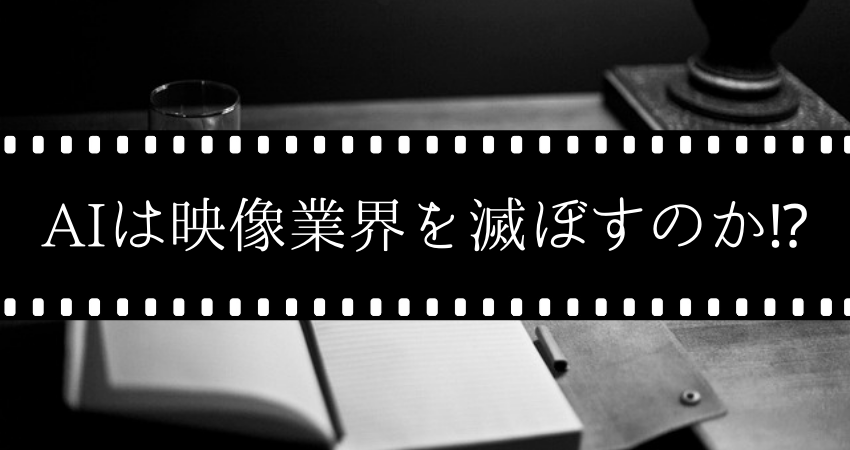
コメント