本は読むのではなく聴く⁉聴学でタイパを最大化する方法
演出部はとにかく読み物が多い
演出部、特に助監督をやっていると「とにかく読み物が多い」とつくづく思います。
その組の台本にしてもペラの台本(ワードデータの準備稿前までの台本)から準備稿、決定稿まで、それがウルトラマンであれば25話分あるのです。
(ウルトラマンメビウスの頃は50話もあって大変だった…)
それにその話に出てくる専門的な知識を勉強するための書籍。
日々の仕事で回ってくるメールや書類関係。
これに加えて自分の知識をつけるための自己投資としての読書を合わせるといくら時間があっても足りなくなります。
特に映像の人間は読書以外にも映画やドラマを見なければならないので尚更時間がない。
特に最後の自己投資としての読書は他に仕事で読まなければならないモノや、仕事をこなしているとついつい後回しになって読まなくなってしまう事がとても多いのです。
特に私は本を読むのが遅いたちなので、なおさらです。
そこで私は一度自分の一日のタイムスケジュールを作ってみたところ自分にはかなりのロス時間がある事がわかりました。
それはスタッフルームや、スタジオに行く移動時間です。
車で家から出発すると大体1時間30分ぐらいかかり、それが一日往復で3時間もありました。
単純計算でも1日3時間、5日間で15時間、1ヶ月60時間=2日半ぐらいを移動時間で無駄にしていた事が分かったのです。
「これは勿体ない」この時間をどうにか自己投資に活用できないかと考えた私は「聴学」にたどり着いたのです。
隙間時間を有効活用するには「聴学」が一番
聴学とはまさに「聴いて学ぶ」事です。
昔はよく英単語のCDを聞いて覚える学習法がありましたが、今では書籍をプロのナレータ―の方が読んでくれるオーディオブックアプリがかなり進化しています。
そもそも人は常に目を酷使して仕事をしています。
一日中パソコンや書類を見て仕事をしていると、目はかなりの疲労を蓄積しています。
そんな時でも耳は元気なままなので、一日の終わりに耳で聴くだけでも疲労感はあまりありません。
それに知識を身につけるには何度も同じ本を読むことが大事ともいいます。
しかし、こんなに時間の無い中で同じ本を何度も読む方が難しい。しかし、隙間時間に耳で聴くだけならアプリがあればすぐにできますし。そこまで難しい事ではありません。
この聴学についてとても分かりやすく解説してくれる動画があったので、ぜひこちらも参考にしてみてください。
フェルミ漫画大学「【要約】超効率 耳勉強法【上田渉】」
YouTube
聴学で得たメリット
私は通勤の車の中でAmazonのAudible(オーディブル)聴いています。

ここでは聴学で得たメリットをお伝えしていきます。
本を読むのではなく「聴く」という新しい視点を取り入れる事で様々なメリットが生まれました。
知識を得る方法は一つではない
聴学を始めて気づいたことは「本は読まなければいけない」という固定概念が捨てれたという事です。
知識をつけるためには本を読むことが一番いいと言います。それは確かですし、本は読む方が頭に定着します。
しかし本を読むことの最大の目的は「知識を得る事」です。
忙しく本が読めないよりも、本を耳で何度も聴いて色々な知識を得る方が何倍も自分のためになる。
「本を読まなくてはならない」というのは手段が目的化してしまっていたのだと気付きました。
この固定概念が無くなった事は自分の知識への挑戦を広げたと思っています。
難しい書籍に挑戦しやすい
耳で聴くだけなので以前では嫌厭して読むことが無かったであろう書籍も気軽に聴くことができ、意外な発見をすることもあります。
難しい書籍と思っていても聴いてみたら意外に聴きやすく知識がすんなり入ってくるのです。
もし難しい内容で頭に入ってこなければまた別の書籍にすぐ移ることも出来ます。
Audibleは月額のサブスクリプションなので、気軽に別の本を聴くことができるので難しいと思っても気にすることはありません。
また、そうやって色々な書籍を物色する事で自分に合った書籍を見つける事が出来き、実際に書籍を購入したこともあります。
本の要点を理解する力がつく
今まで、本を読んで理解するのに苦労をしていましたが、「本を聴いて、理解する」という聴学をやっていると様々な本を聴くことになります。
すると本には大体、大きな要点がいくつかあり作者の伝えたい要点が何かわかるようになってきます。
これはいくつも本を読んでいる人であれば理解している事ですが、本には作者の伝えたい事があり、その根本の部分が読み取れれば後は読み流しても問題なかったりします。
この要点を理解する力が聴学で多くの本を聴いていると身についてきます。
これは実際に本を読む時にも応用でき、本の要点が分かるようになっていました。
何度も言いますが、本を読むことの第一目的は「知識を得る」こと。
そのために様々な本を選び、とりあえず聴いてみるというのは聴学の醍醐味ではないでしょうか。
- 手軽に知識を得る事が出来る
- 様々な本に挑戦しやすい
- 本の要点を理解する力がつく
- 「読まなければいけない」という固定概念をなくせる
このように隙間時間に知識を得るにはとても良い「聴学」
下記に聴学を始めてとても身になったおすすめの書籍をご紹介します。
プロだけが知っている小説の書き方
著者: 森沢 明夫
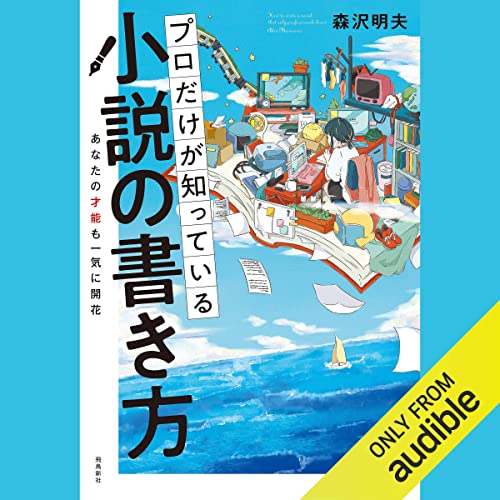
魅力的な小説を書くには何が必要か、物語におけるキャラクターの重要性、またキャラクターのつくり方など脚本にも応用できる素晴らしい書籍。
デール・カーネギーの人を動かす方法
著者: デール・カーネギー, 関岡 孝平
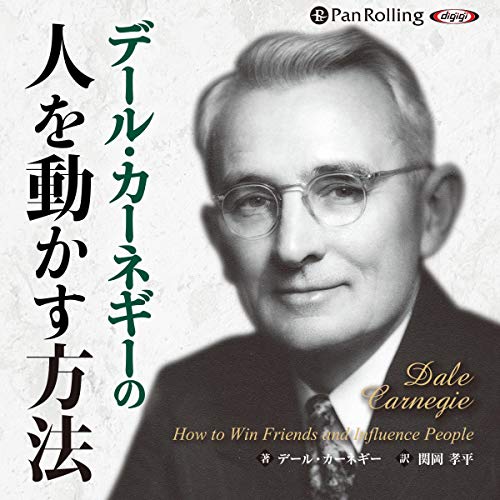
作家にして対人スキルの研究者デール・カーネギー氏による名著。監督や助監督として人と対話する時などとても参考になる。社会人の必読書。
夢をかなえるゾウ
著者: 水野 敬也
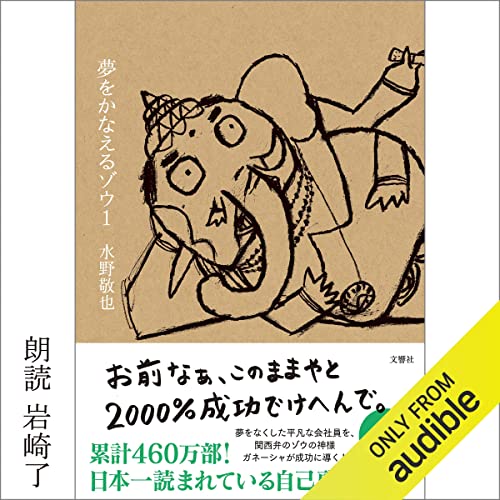
インドの神「ガネーシャ」がうだつの上がらなサラリーマンに成功の秘訣を説く小説風自己啓発書。自分が人生を見つめなおすきっかけになった本。
オーディオブックのデメリット
ここまで聴学のメリットをお話してきましたが、もちろん全ての人におすすめという訳ではありません。
ナレーターが本を読むのを聴くという独特の学習法が合わない人もいると思います。次は自分が感じたオーディオブックのデメリットをお伝えします。
覚えがある人はもしかしたら聴学に向いていないかもしれません。
飛ばし読みがしにくい
オーディオブックはナレーターが本を読んでいく性質上その進行が読み手に委ねられます。
そのため本特有の「一部の章に飛んで、部分だけを読む」という方法がとりにくいです。
もちろんオーディオブックにも章分けはされていますが、一部だけをピックアップして聴いたり、戻って聴くという操作はしにくく、基本的には順番に流しながら聴いていく学び方になります。
本のようにある内容を索引するというのもしにくいのが特徴です。
読む速度、読み方はナレーターに次第
オーディオブックはナレーターが本を読む性質上、読む速度はナレーターに委ねられます。
もちろん倍速再生など速度は割と自由に変更できますが、速くしすぎると理解できないぐらい速くなるので普段から早く読んでいる人にはもどかしく思うかもしれません。
またナレーターの声が合わないという人もいるでしょう。
複数のキャラクターや女性の声を男性ナレーターが一人で演じる場合があるのでそれが生理的に合わないと感じる人もいるかもしれません。
月額の利用料が掛かる
オーディオブックのアプリは月額課金のサブスクリプションが基本です。
そのため、アプリを入れたが一か月も何も聴かなかったとなるとただお金がかかるだけなので、勿体ないです。
例えばAudibleは月額1,500円なので、年間にすると1万8000円と割とサブスクリプションにしては高い金額設定となっています。
なので無料体験のキャンペーンなどで続けていけそうか試してみる事をおすすめします。
ただ、続けていくのであれば毎月新書を1冊買うぐらいの金額なので、毎月数冊聴けば簡単に元は取れます。
以上のようにメリット・デメリットはありますが「知識を得る」という事に関しては聴学はとてもタイパが良く、隙間時間には持ってこいだと思います。
ぜひ通勤時間にゲームなどで時間をつぶすのではなく「聴学」で自己投資をしてみてください。
その小さな差がやっている人とやっていない人で大きな差になる事は間違いありません。
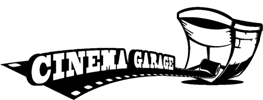

コメント